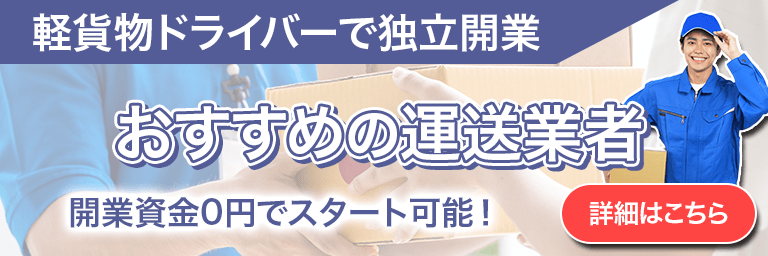軽貨物運送業界は、ネット通販の拡大や個人配送の需要増加にともない、今後ますます成長が期待される分野です。低コストでの独立開業が可能であるため、多くの人びとが新たなキャリアとして選択しています。そこで本記事では、軽貨物業界の今後の展望や将来の課題について詳しく解説します。
軽貨物運送業について
軽貨物運送業とは、軽自動車を使用して有料で荷物を運ぶ運送事業のひとつです。主に軽トラックや軽バンといった軽貨物車を使用し、この車両には黒ナンバーと呼ばれる特別なナンバープレートが付けられているのが特徴です。
この黒ナンバーを取得することで、軽貨物車を使った運送業を合法的に営めるようになり、軽貨物運送業として事業を展開する際の基本的な要件を満たします。
女性やシニアでも働きやすい
運送される荷物は、軽くて小さなものが中心で、日常生活のなかでよく目にするような、片手で持ち運べるサイズの荷物が多く、ネット通販の配送や宅配便、小型の引っ越しなどの場面で活用されています。
大規模な荷物を扱うことが少ないため、女性ドライバーやシニアドライバーなど、比較的幅広い層の人びとが参入しやすい業界となっています。
軽貨物運送業が注目されている理由
軽貨物運送業が注目されている理由のひとつに、大型トラックの運送業と比べて体力的な負担が少ないという点があります。大型トラックは重い荷物を積み下ろししたり、長距離を走ったりするため、ある程度の体力が必要です。
しかし、軽貨物車を使用する運送業は、比較的軽い荷物を運ぶことが多く、短距離の配送が中心であるため、ドライバーの身体的な負担が少ないのが特徴です。また、軽貨物運送業では普通自動車免許さえあれば始められる点も魅力のひとつでしょう。
自由な働き方が可能
個人事業主として軽貨物車を使った運送業を営む場合、勤務時間や働く場所を柔軟に選べるため、副業として始めたり、主婦や高齢者が家事や育児と両立しながら働いたりできます。また、ドライバー自身が自分のペースで仕事を進められるため、過度な負担がかからない点も、軽貨物運送業のメリットといえるでしょう。
軽貨物運送業の現状
軽貨物運送業の現状は、ネット通販の拡大や個人配送の需要増加により、常に高い市場規模を維持しています。軽トラックや軽バンなどの軽貨物車を使用した配送サービスは、都市部だけでなく地方でも高い需要があり、日々多くの荷物が軽貨物ドライバーによって運ばれています。個人事業主として働く軽貨物ドライバーも増えているのが現状です。
軽貨物運送業の収入面
収入面では、軽貨物ドライバーとして得られる年収は、個人事業主の場合で300〜399万円がもっとも多いとされています。これを月収に換算すると、約25〜33万円です。ただし、この金額はあくまで売上ベースであり、実際に手元に残るのは経費を差し引いた金額となります。
経費には、燃料費、車両のメンテナンス費用、保険料などが含まれます。とくに車両の維持管理は欠かせないため、これらの費用が積み重なると、収入の手取りはさらに減少することがあります。そのため、効率的な業務運営や経費管理が重要です。
詐欺的な行為に注意が必要
軽貨物運送業において注意すべき点のひとつは、詐欺的な行為が蔓延していることです。軽貨物ドライバーを対象にした詐欺行為として、高額な手数料や不当なマージンを請求する業者が存在します。
たとえば、配送の仕事を紹介すると称して、契約時に不当に高額な費用を請求するケースや、実際にはほとんど仕事がないのに業務委託契約を結ばせ、高額なマージンを取るといった詐欺が報告されています。
これにより、多くのドライバーが大きな経済的な損失を被ることがあります。そのため、契約前にしっかりと業者の信頼性を確認することが重要です。
体力的な負担がかかりやすい
軽貨物運送業は、体力的な負担がかかることも事実です。軽貨物車を使用するため、大型トラックのように重い荷物を扱うことは少ないものの、日常的に車を長時間運転する必要があり、また配達先では階段の昇り降りを頻繁に行うこともあります。
エレベーターのない建物での配達業務は、体力的に厳しい場合があり、若い人でも疲労が蓄積しやすい環境です。このように、軽貨物運送業は体力に自信がない人にとっては辛い仕事になるため、適切な休憩を取りながら業務を行うことが求められます。
繁忙期が存在する
軽貨物業界には繁忙期が存在し、その期間はとくに忙しくなります。お中元やお歳暮のシーズンなど、贈り物や商品の配送が増える時期には、朝から晩まで休みなく働くことが珍しくありません。繁忙期には、通常の配送業務に加えて特別な配送依頼が増えるため、一日中運転をしても配送が終わらないことがあります。
個人事業主として働くドライバーにとっては、繁忙期は収入を増やすチャンスである反面、過度な負担がかかる時期でもあります。そのため、体力的な準備をしっかりとしておくことが重要です。
軽貨物運送業の今後
軽貨物運送業の今後を展望すると、この業界が消滅する可能性は極めて低いといえるでしょう。現代社会におけるネット通販やオンライン注文の増加により、軽貨物配送の需要はますます拡大しています。とくに、個人宅への小口配送が主流となっており、軽貨物ドライバーの役割は欠かせません。
2024年問題について
物流業界全体の課題として浮上しているのが、2024年問題です。この問題は、2019年に施行された働き方改革関連法によって定められた長時間労働の制限が、2024年4月から物流業界にも適用されることを指します。
この法律にもとづき、時間外労働が年間960時間に制限され、軽貨物ドライバーには大きな影響をおよぼすと予想されているのです。現在、軽貨物ドライバーは長時間労働をこなすことで収入を確保している場合が多く、労働時間の短縮によって収入が減少する懸念があります。
再配達問題
物流業界全体で大きな課題となっているのが、再配達問題です。再配達は、受取人が不在の際に発生し、同じ荷物を何度も配送する必要が生じますが、ドライバーが得られる報酬は1回分のみです。このため、ドライバーには過剰な負担がかかる一方で、効率的な配送が難しくなります。
再配達を減らすためには、受取側の対応を見直し、宅配ボックスの設置や、地域の受け取り場所を増やすなど、社会全体での対応が求められています。こうした問題の解決は、物流業界全体の効率向上につながり、ドライバーの負担軽減にも貢献すると期待されています。
4ナンバー以外の車両でも運送が可能に
2022年10月に規制緩和が行われ、貨物専用の4ナンバー以外の車両でも軽貨物運送が可能となりました。これにより、5ナンバーでも、届出を行うことで軽貨物運送業が営めるようになっています。この規制緩和は、慢性的なドライバー不足を解消するための一助となる可能性が高いと期待されています。
安全面でのリスクが増大する可能性
新規参入者の増加にともない、運送技術のスキル低下や、運送賃金の低下も懸念されています。経験の浅いドライバーが増えることで、配送の質が低下したり、安全面でのリスクが増大する可能性があります。
また、新規参入者が多くなることで、競争が激化し、運送料金が引き下げられる懸念もあるでしょう。この影響は、現在すでに軽貨物運送業に従事しているドライバーにとっては収入減につながる可能性があり、業界全体のバランスが崩れるリスクも存在します。
まとめ
軽貨物運送業は、ネット通販の拡大にともなう高い需要を保ちながらも、人手不足や再配達問題、さらに2024年問題など、さまざまな課題に直面しています。規制緩和によって新たな参入者が増える一方で、ドライバーの負担や収入減少への懸念もあるのです。今後、業界で成功するためには、効率的な業務運営やスキル向上、そして社会全体での再配達問題の改善が求められます。軽貨物運送業は、柔軟な働き方を実現できる魅力的な業種であることは間違いありませんが、時代に合わせた戦略が必要不可欠です。